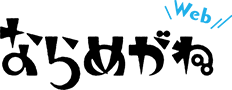僧侶にしか撮れない写真とは?

ここから、寺院スタグラムの核心となる質問をしていきますね。
「一般人が撮る写真」と「僧侶が撮る写真」、その大きな違いは何だとお考えですか?
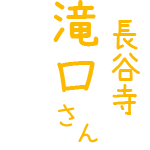
単に境内の風景を撮る場合は、そんなに違いが出るものでもないように思います。
ただ、私は長谷寺の僧侶であり職員なので、ご本尊の観音さまであったり、同じ僧侶の姿であったり。
そういったものを間近で撮ることができるのは、一般の人とは違うかなと思います。法要の写真もそうですね。

法要のシーンを一般人が遠くから望遠レンズで撮ることもあるかと思いますが、お坊さんからしたら「それは見当違いのところを撮っているよ」ということも?
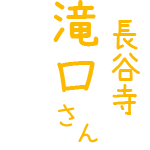
そうですね。「法要の中で核となる部分がどこか」こちらはわかっていますので。
そこにカメラを向けられるかという点で、違いは出てくると思います。

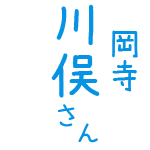
瀧口さんが言うように、我々は法要の写真や動画を撮って、皆さんに知っていただくことがあります。
ただ、今ここに集まっている4寺院はみんな真言宗系(密教)なので、「オープンにしていいこと」と「ダメなこと」があって。
そういった意味で、単にお祭りや儀式をぱっと外から撮るのではなく、「守るべきところは守って写真を撮れる」というのが一般の方との大きな違いですね。
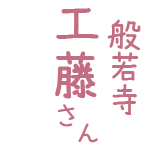
同じ風景を見ていても、見え方というか、捉え方に違いがあるかも。
例えば、姫睡蓮(ひめすいれん)の花の中にちっちゃな水滴ができることがあるんです。「それが仏さまに見えてきた」っていうのは、仏教者ならではの感覚だと思うんです。

お寺の前の道を歩く回数って、おそらく一般の人たちは2、3回ほどだと思いますが、私たちは何千回、何万回と同じところを歩くわけです。
そこで、「あ!」と気づくことが非常に多くて。「ここからこう見たら、すごくきれいだよ」って。

室生寺さんといえば、写真家・土門拳が通い詰めた古刹としても有名ですよね。

はい。室生寺は写真を撮る聖地みたいなお寺なんで、写真の上手な人もたくさん来られるんです。
そういう人たちに比べたら、私は上手に撮れてないかもしれませんが、自分の中では「このお寺の本当に素晴らしいところを知っている」っていう感覚なんです。


先ほど、般若寺の工藤さんから姫睡蓮(ひめすいれん)の花の話がありましたけど、室生寺があるのは龍神さんの地なので、「あ、龍いる」と思うときが、けっこうあるんです。何かパワーを感じながら撮っているというような…。
「今すごいことが起こってるぞ」っていう感覚になるのは、一般の人たちにはあんまりないことかも。
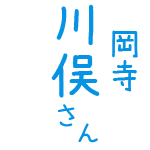
それとやっぱり、僧侶と一般の人との違いは、仏さまを近くから撮れるところ。
仏さまの撮影は、お寺によっていろいろ対応も違いますが、昔から岡寺では「堂内で写すのはやめてください」と皆さんにお願いしてるんです。特にご本尊さまですけど。
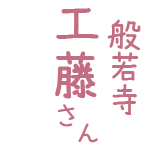
般若寺でもたまに、本堂の仏さまをちょっと離れたところから望遠レンズで撮ってる人がいて。
もちろん注意するんですけど、正直「その写真どうすんねん?」って思うんですよ。
「現像して拝むなら、別に撮ったらええわ」って思うんですけど、たぶん自慢するだけの写真…。
しかも、ちゃんとした形で撮っていない。

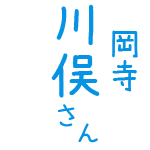
写真を撮って現像して、それをきちんとお祀りしてくれるならいいけれども、おそらく粗末に扱われてゆくのだろうと。
それはイコール、仏さまを粗末に扱ってしまうということにつながりかねません。
僧侶が仏さまを撮影するとき、「撮った写真ですら粗末にはできん!」という気持ちを持って、写真に納めさせていただいています。
そこにあるのは、やっぱり信仰心なんです。

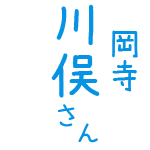
我々は“仏さま”として見ているんですが、単に仏像というか、美術の作品を撮るみたいな感覚で撮られている方も、中にはいらっしゃる。
そういう方たちとは、仏教者として一線を画すというか、明らかな違いが出てくるのかなと思います。
すべては100年先につなげるため

いちばん聞きたかったことをお聞きします。
お寺としてインスタを発信する意義とは、何だとお考えですか?
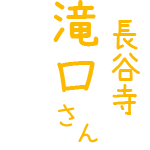
インスタグラムは、お寺を知ってもらう「一つのきっかけ」と考えています。
あくまで、その奥にある「長谷寺」というものを知ってもらうための「さわり」であって、インスタグラムだけですべてを伝えられるとは思ってなくて。

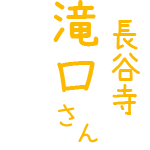
長谷寺には長い歴史の中で、故事や伝承がたくさんあります。
「こんなのがありますよ、こんなのもありますよ」って感じで、その引き出しの中を少しでも垣間見てもらい、そこから長谷寺を知ってもらう。それに尽きますね。

やはり、お寺って、ただでは運営できないんですよね。
お一人おひとりに入山料を払っていただいて、それで仏さまを修復したり、お堂の屋根をふき替えたりして、維持してるのが現状で。
人が来てくれないと、いつか途絶えてしまう。それが一番怖いんです。

歴史ある文化財を維持するのは、一般人が想像する以上に大変なことだと聞いています。

お寺は金儲けしてるって、汚いものを見るような目で見る人も、中にはいるかもしれない。
でも、自分たちの代で右肩下がりには、絶対したくない。
むしろ、後世に対してちょっとでも、「前の世代の人たちが力を尽くしてくれたから、今の室生寺がある」って思えるような形でパスしたい。


確かにインスタグラムは手段の一つでしかないけれど、それをきっかけにお寺に来てもらえたら、大変ありがたいです。
私としては、「あなたの入山料で室生寺が保たれているんですよ」ということをいろんな人に伝えたい。
それこそ「室生寺は私が支えています」っていうぐらい、お寺を身近に感じる人が増えていくきっかけになったらいいなと思ってます。
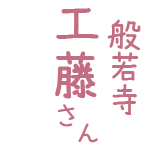
お坊さんっていうと、「法事いって」「お葬式いって」というイメージがどうしても先行してしまって。
それをインスタで払拭したいというのも、一つありますよね。
今ここに集まってるお寺さんはみんな、歴史も古く、拝観料だけでやってはるとこばかり。
「でも、実はお寺はこんなこともしてるんです」って知ってもらうには、インスタってすごい使えますよね。

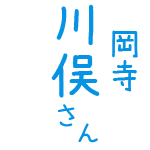
今回のコロナ禍を受けて、岡寺では疫病退散のお札を出させていただきましたが、それは江戸時代の版木が残っていたからなんです。
▼そのお札の記事はこちら。「日本初の厄除け霊場・岡寺で、悪病退散の祈祷札を授与」
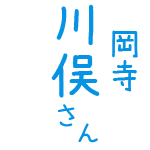
今、我々が苦しんでいることは、過去に先祖さんたちも経験していること。お寺にはその情報が蓄積されている。だから、こういうお札も残っていて。
長谷寺さんだったら、明治のときのコレラ?
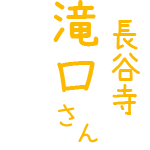
そうです。かつて長谷寺も、明治時代にコレラが流行ったとき、疫病退散のお札を出しました。
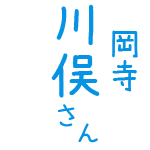
今回のことで、「お寺には人々の知識とか経験知というのが詰まってるんだな」とすごく感じました。
そういった先人の教えを、少しずつでも今の時代に出していくという意味で、インスタなどのSNSは、現代に合ったアウトプットの仕方になるんだろうなと思います。
「お寺って、昔から人々のためにこういうことをしていたんだ」と知っていただけると嬉しいですし、それがお寺に足を運んでいただくきっかけになれば。

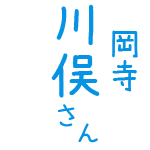
室生寺の山岡さんも言っていたように、皆さんに支えていただくことで、お寺を後世に残していきたい。
そうすれば今から100年後、「岡寺では100年前にこんなお札を出して疫病退散してたんだよ」ってことがまた、わかることになります。
いかにして後世につないでいくか。大きな役割を、我々は担っているのかなと思います。
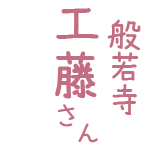
そういう意味では、恥ずかしいことできないですよね。
インスタって、すぐ広まるじゃないですか。その責任は重いっすよ。
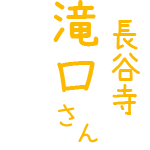
いい時代やと思いますよ。
今までは、お寺から出したい情報はテレビや雑誌のフィルターを通してしか出せなかった。
それが今はダイレクトに皆さんに届けられる。
インターネットが発達して、人々との距離が短くなった。本当にありがたい時代だなあと思います。
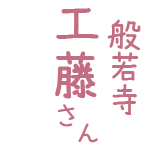
長谷寺さんは、全国的に見てもフォロワー数トップ!
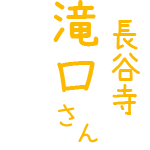
一番多いのは京都のお寺さんです。うちは、仏教のカテゴリーでは2番目。
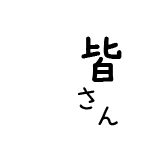
へぇー!?
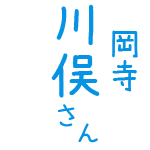
でも実質1位やね。
長谷寺さんは、僧侶の瀧口さんが写真を撮って投稿してるけど、向こうさんはプロのカメラマンも入ってはるんちゃう?
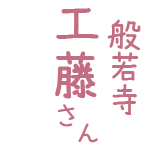
後世には、“インスタ大師”ですね!

功績を讃える彫像が立っているとか(笑)

錫杖(しゃくじょう)の代わりにカメラ持って(笑)
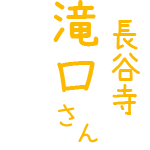
持物(じぶつ)になったりして(笑)
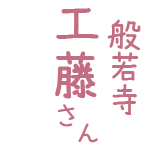
それは、撮っていい仏さま!(笑)
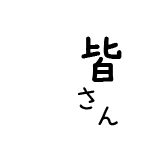
(爆笑)

これにて、Vol.01 終了です! ありがとうございました。

次回、Vol.02は「#僧侶たちのマイカメラ」と題し、4寺院の僧侶が実際に使っているカメラやレンズを公開。
また、最近の4寺院の投稿の中から、編集部がぐっときたインスタ写真を厳選してご紹介します。お楽しみに!
2020年7月10日公開
土門拳が常宿にした空間で、写真を語る

今回、Special座談会を行ったのは、室生寺門前にある明治4年創業の老舗料理旅館「橋本屋」。
昭和を代表する写真家・土門拳が室生寺に通い詰めた際、常宿としていた風情ある旅館で、写真を語るのにこれほどふさわしい場所はありません。
奈良に来たら、ぜひ一度泊まってほしい大人の名宿です!
また、向かいにある系列店「御食事処 橋本屋」では、大和芋をすり下ろした「すまし汁」が付く丼など、気軽に味わえるメニューをいただくことができます。



橋本屋(はしもとや)
住所 奈良県宇陀市室生800
電話 0745-93-2056
料金 1泊2食付 1万5000円(税別)
※宿泊は1日2組限定
HP hashimotoya-uda.jp
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、現在宿泊はお休みしています。
※「御食事処 橋本屋」は営業しています。
岡寺 [ 詳細情報はこちら ]
長谷寺 [ 詳細情報はこちら ]
室生寺 [ 詳細情報はこちら ]
般若寺 [ 詳細情報はこちら ]
※本記事の取材・撮影は2020年6月、新型コロナウィルス感染拡大防止の対策を講じた環境のもとで行いました。
※記載の情報はすべて同年6月末現在のものです。
取材協力/岡寺、長谷寺、室生寺、般若寺
撮影協力/橋本屋
聞き手・文/ならめがね編集部、上乃ゆか
撮影/中井秀彦